こんにちは、ito(@itokake_labo)です。
「もっと○○があれば…」と思いながら毎日を過ごしていませんか?
私も長い間、「ない」ものばかりに目を向けて苦しんできました。でも、ある視点の変化が私の日常を少しずつ変えていったんです。
この記事では、決して「今に満足しろ」という正論ではなく、どんな状況でも自分の心を守る小さな習慣をシェアします。つらい日々の中でも、少しだけ息ができる場所を見つけるヒント、最後まで読んでいただけたら嬉しいです
「ありがとう」の前提にあるもの
突然ですが、昨日あなたは何回「ありがとう」と言いましたか?
「ありがとう」の語源は「有り難し」。
つまり「あることが難しい」=「あって当然じゃない」という意味なんです。
日常では、家族が帰ってくるのも、健康で過ごせるのも「当たり前」になりがちですが、本当はそれ、奇跡のような出来事かもしれません。
たとえば、家族が事故に巻き込まれてもおかしくなかった、とあとから知ったとしたら?
帰ってきた家族の顔を見るだけで、涙が出るほどの感謝が湧きませんか?
人は、自分が「知っていること」や「当然だと思っていること」を前提に、日々を過ごしています。
でも、その“前提”って、実はとても狭い枠の中の話だったりする。
現実には、私たちが気づかないところで「起きていること」がたくさんある。
ただそれを知らないだけ。見ていないだけ。
あなたはどう感じるでしょうか?
交通事故に遭う確率は、1年間で0.2%。つまり、約500人に1人が交通事故の被害者になっている、ということなのです。
一生のうちに交通事故に遭う確率は約25%。これは4人に1人が交通事故に遭ってしまうということを示しています。
もしあなたが、初めてこの情報に触れた場合、すでに帰宅している旦那様やお子さんのお顔を見て、感情に変化はないでしょうか?
それらの情報を知り、あったかもしれない辛い世界をありありと感じた瞬間、今ある幸せに感謝しませんでしたか?
自分の信じている『当たり前』を知る
知らないだけで、様々なことが現実世界には起こっています。
ただ単純に認識していないだけ、ということは多い。
「当たり前」に思っていた日常のひとつひとつが、実はかけがえのない“ある”だったと気づくと、世界の見え方がガラッと変わります。
「ない」ばかり見つめてしまう私たち
でも、私たちは「ない」に敏感です。
・もっと収入があったら…
・もっと子どもが言うことを聞いてくれたら…
・もっと夫が協力してくれたら…
つい「足りない」ものばかり探してしまうクセが、誰にでもあります。
SNSや他人と比べては、自分の「ない」にフォーカスして、勝手に落ち込んでしまうこともあるかもしれません。
でも、もしあなたのお子さんが「〇〇ちゃんはできるのに、私は…」と落ち込んでいたら、あなたはきっとこう声をかけますよね。
「できてないことばっかりじゃなくて、あなたが“できていること”もちゃんと見てあげて」って。
それは、大人の私たちにも同じはず。
幸せの土台は、「ある」を見つける目
大切なのは、「ない世界」を知った上で、自分に“あるもの”をちゃんと見てあげること。
比べるなら、優劣ではなく“違い”を知るためにしたい。
誰かの「ある」は、自分の「ない」と比べるためじゃなく、
「私は私の“ある”を育てていこう」と思えるためのヒントにしたいですよね。
絶望の中でも「ある」を見つけた人たち
ナチス政権の最大の犠牲者を生んだアウシュヴィッツ収容所。
収容所から生き延びた人々に共通していたのは、どんな状況でも「心だけは支配されない」と決めていたことだったそうです。
希望や愛や信念といった、“見えないけれど確かに“ある”もの”を、自分の中に育て続けていたんです。
物質的に「ない」世界に身をおいていても、心まで「ない」にしない覚悟を持ち続けていた。
『世界でいちばん幸せな男』(エディ・ジェイクさん著)は、そんな心の在り方を、私に教えてくれた本の一つです。
読むのが辛い部分もあるかもしれません。
でも、もし「幸せ」って何だろう?と本気で考えたい人には、ぜひ手に取ってほしい一冊です
読んでいただきありがとうございました
▶︎別途アメブロでオンライン秘書についての情報発信中➡︎ 【アメブロを覗いてみる】 ポチッ

この記事が気になったら
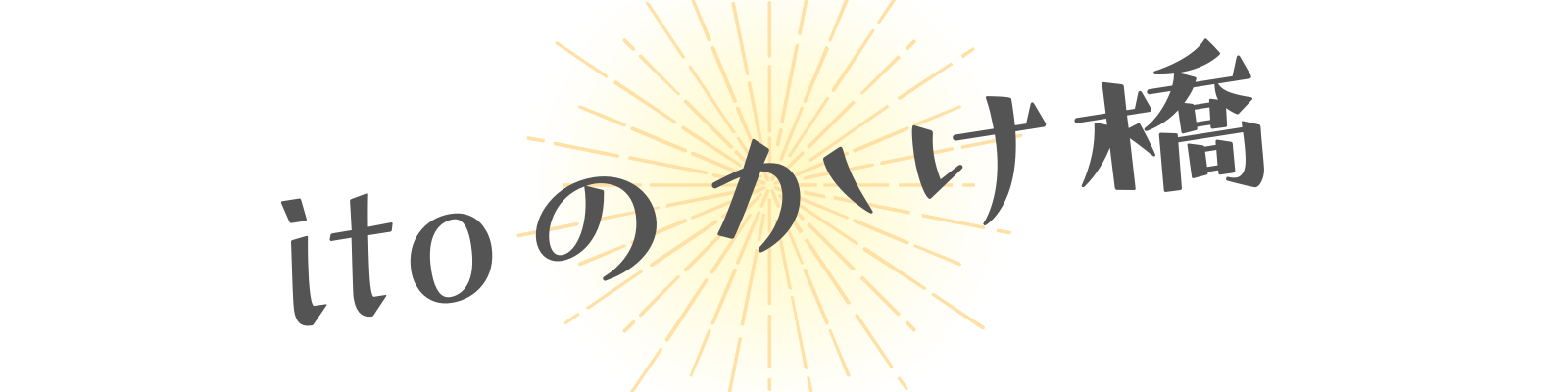

.png)
