こんにちは、ito(@itokake_labo)です。
子育てに完璧を求めていませんか?
実は、「完璧な親」を目指すことが、子どもの成長の妨げになっているかもしれません。
このブログでは、親の不完全さが子どもの自立心と柔軟な思考力を育む理由と、多様な価値観を伝えることの大切さについてお話しします。肩の力を抜いて、あなたらしい子育てを見つけましょう
お母さんの子どもへの影響力
お母さんというのは、どうしたって子どもとの時間を多く持つ傾向にあります。
妊娠期には常に一緒に生きていますしね。
そしてやはり、その分、子どもへの影響も・・・
この話・・・責任感が強い方ならば、心がズーンと重くなるものかもしれませんね。
もしかしたら、仕事に、子育てに奮闘し続けている方は、この先を読もうか迷うかもしれません。
母親の子どもへの影響力なんてわかってる!だから余計に辛いんだ!と。
子どもを人質に取られているような感覚。
自分の自由を選ぶと、「子どもはどうなってもいいのか?!」と、どこからか聞こえてくるようだと感じる人もいるのではないでしょうか?
私自身、まさにそんな風に感じることがありました。
『私の自由』や『私の幸せ』を、時に『子どもの幸せ』とのトレードオフだと感じていたんです。
なぜなのか。
それは、“子育てに苦しんできた親”を見てきたからだと思うのです。
親が、特に(私の育った家族においては)母親が、沢山たくさん”我慢”をして子どもを育てているように見えていたから。
親も完璧ではない
長年私は、AC(アダルトチルドレン:子ども時代の家庭環境や親の行動に起因する心の傷を持つ大人)に当てはまるような特徴を多く持っていました。
他のブログ記事を読んでくださった方は、すでに感じていらっしゃるかもしれません。
ただ、自分の境遇から『心と脳』についての興味が高まり、心理学や脳科学等の学びを深めていく中で、気がついたことがあるんです。それは…
アダルトチルドレンの特徴は、どんな人でも大なり小なりあるのではないか?ということなんです。
両親の不仲、家族間の不和、離婚、家族との関わりの中でできた悲しい記憶・・・。
それらを全く感じずに成長した人の方が少ないように感じます。
一説によれば、日本人の8割がアダルトチルドレンなのだそうです。
おそらく、時代の転換期にあたり、“親世代の常識(主に子ども時代に培われたもの)”が“子ども世代の常識”と大きくズレていったことも原因の一つでしょう。
だからこそ、このブログでは、「アダルトチルドレンである私」とは書きませんでした。
それは、専門家の診断を仰いだことがないという背景もあります。
ただ、長く、それに当てはまる症状で苦しんできたことは事実としてある。
そして、家族がこんな形だったなら、、、と何度も何度も考えたことも。
私以上に、アダルトチルドレンの症状で長年とても苦しんでいらっしゃる方がいることも、理解しているつもりです。
自分が体験していることのレベルを、誰かと比べることは、とてもとても難しい・・・
辛かったことは事実。ただ、私の場合、自分の理想を叶えるために、『アダルトチルドレン』と自分を紐付ける選択は、足枷になり得るものでした。
私は、『アダルトチルドレンである私』を手放す方が、自分にとって心地がよかったのです。(HSPの特徴にも当てはまることも沢山あり、よくわからないということも正直あります。知ることは大切。ただ、私の描いている理想の人生において、それを掘り下げる必要はないと今は感じています。)
これは決して、アダルトチルドレンやHSPを否定しているのではありません。
自分の経験から、”大人の言葉による子どもの心への影響”を心配するあまり、(自分が言ったあの言葉、自分がしたあんなことが、子どもの人生に大きな負の影響を与えることにはならないだろうか?)と、私はいつも考えていました。
そして、実家や義実家に行った際に、祖父母が我が子にかける言葉にも、(これは子どもにとって負の影響を与えはしないだろうか?)と敏感に反応していました。
でも、心と脳の学びを深め、実生活で多くの実験を繰り返していく中でわかったことがあります。
どんな自分であろうと、『自分が思う子どもにとってのプラス』を差し出すことしかできない。
それならば、まず様々なことを知り、その中で自分が信じた『子どもにとってのプラスとなるもの』をやろう。
そして、自分は完璧ではないことを常に肝に銘じ、子どもを観察していこう。
お母さん=いつも正しい!!を目指さない
子育てに完璧は不要。
むしろ完璧だと思ってやることの方が、本当は危険です!
親はどうしたって、子どもを『洗脳』してしまう。
これは、認知科学者の苫米地英人さんがおっしゃっていることです。
苫米地英人さんがおっしゃる通り、親はどうしたって子どもを『洗脳』してしまうと思うのです。
なぜなら、「これがいいこと(正しいこと)だ」と思っていることを繋ごうとするのが躾だから。
「手で食べないで、お箸で食べなさい!」だって、文化が変われば正解ではありません。
「宿題やったの?」だって、強く言い続ければ、「与えられたことは必ずやりなさい」と、子どもの選択の幅を狭める結果になってしまうかもしれません。
前提が変われば、その躾は呪縛になってしまうことはどうしたって起こり得る。
そういう意味で、親はどうしたって子どもに「これがいいこと」を与え続けてしまう。
『洗脳』になってしまうんです。
じゃあ、どうすりゃいいのよ。
何を言うのも、何をするもの怖くなるわ。
この恐怖は、少なからず多くの親が感じていることではないでしょうか?
誰か答えを教えてよ。
私もそうでした。
だからみんな、ネット検索をしたり、子育て本を読んだり、時には情報を集めたくてネットワーク(ママ友などなど)に頼るのではないかと思うんです。
親にできることは限られている。
そして、親は良くも悪くも子どもを『洗脳』してしまう。
それを知って、受け入れていることが重要なのではないでしょうか。
どうせ洗脳してしまうなら、子どもの自信や未来への希望を高めるものにしたいですよね。
そして、親である自分がしてしまう『洗脳』に繋がる躾を、”唯一の正解”にしない余白作りを。
私は、『教育』こそ一番親のリソース(時間やお金等)をかけるところだ!と考えているのですが、それはこのことが前提にあるからなんです。
『教育』というと厳かな感じがしますが、親の価値観だけに染めないために、多様な視点を、多様な価値観を、多様な世界を見せて、体験させてあげること。
そしてそこから、自分で自分の人生の選択(自分の幸せに繋がる選択)をしていけるようにサポートすること。
人と生きるために『正解は1つではないこと』を繋いでいく
人と生きるということは、様々な価値観を持った人と出会うこと。
だから、親である“私”や、“我が家”と明らかに考えが違う人と接することも、子どもにとっては生きる上での一つの体験。視野を広げるための一つの出会いではある、と今は捉えています。
例えば、日本を離れて別の国に少し住んでみると、常識の違いに驚くことは多いです。
「え、これでいいの!?」
「え、日本もこうすればいいのに〜」
違いに触れることは、自分の『当たり前』や『常識』を認識する機会になりますよね。
子どもに自分軸に沿った人生を歩んで欲しいのなら、違いを認めることは大事ですよね。
違いを認めるためには、『自分の思いや考えは、あくまで自分のものである』と受け入れることから始まります。
今日のブログは、『子育て』にだいぶ寄せて書いてしまったのですが、子どもに対して意識することは、自分に置き換えて考えてみると、さらに理解が深まるのでおすすめです
多様な視点を、多様な価値観を、多様な世界を自分で見て、そこから『”正解”は無数にあること』を体験し、『自分の思いや考えは、あくまで自分のものである』と受け入れることができれば、子どもの想いを受け止め、子どもにも違いを認め、それと交わって生きることの素晴らしさを伝えていけると感じるから
物事に貼るラベル。それはある枠組みを『カテゴライズ』することにも繋がります。
『カテゴライズ』による思考の制限は、行動の制限に繋がる。
長年勤めた会社でも、カテゴライズで“自分のできること”に制限をかけていた後輩が、私との関わりの中で、カテゴライズから抜け出し、大きく飛躍した姿を見せてくれたことがありました。
ぜひその話をしたいのですが、長くなったので次のブログでご紹介させてください。お楽しみに
読んでいただき、ありがとうございました
▶︎別途アメブロでオンライン秘書についての情報発信中➡︎ 【アメブロを覗いてみる】 ポチッ

この記事が気になったら
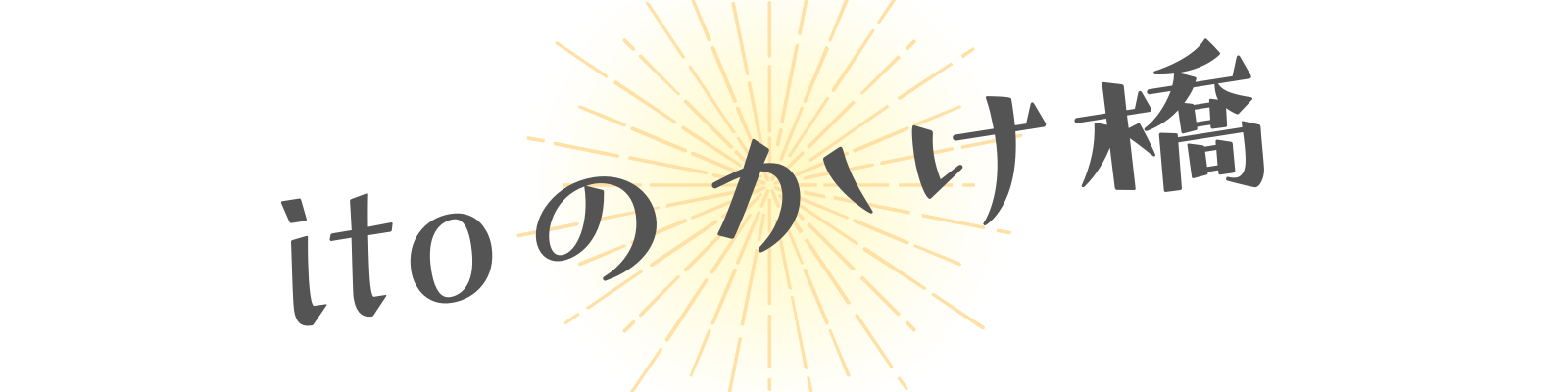

.png)
