こんにちは、ito(@itokake_labo)です。
「毎日頑張っているのに、なぜか満たされない…」そんな思いを抱えていませんか?
本記事では、他者のために生きることから、自分のために生きる決断をした瞬間に訪れる人生の変化について、私自身の経験をもとにお伝えします。慢性的な疲れや不満を感じている働くママの心に、新たな視点をお届けします。
助ける=相手のため、という思い込み
なんだか自分を”慈悲深い人”だと紹介するようでためらわれるのですが、私は様々な場面で悲しんでいる人、苦しんでいる人に対して敏感で、自分がどうにかしなければ!と考える場面が多かったんです。
持って生まれた資質的には、共感性が高いのかもしれません。
会社でも、たとえその対象が明らかに自分より給与をもらっている、役職的にも高い地位にいる人だとしても、その状況についていけない人を放っておくことはできなかったんです。
でも、その人を助けている(と思い込んでいる)間、ずーっとずっと不満を溜めていました。(あ、慈悲深くない本性が・・・笑)
なんでこんなに教えているのにやらないんだろう?
これだけ差し出しているのに、なんで活用してくれないの??!
そうやって、ずっとずっとそんなジレンマと戦いながら(夫に愚痴を言いながら)も、『見捨てない私』を保っていました。
でもある日、とある言葉に出会い、『見捨てない私』の別の側面を知ったんです。
「相手にとって『それが幸せだ』と決めつけるのは、傲慢じゃない?」
こんなに与えてやってるのに。
こんなにも支えてやってるのに。。。
その人が助けて〜という前から、これが必要なんでしょ?これがあなたの幸せでしょ?と差し出す。
これは傲慢ではないか、と指摘されたのです。
中国古代の哲学者である老子の格言に、こんな言葉があるそうです。
『授人以魚 不如授人以漁』
つまり、『魚を与えるのではなく、釣り方を教えなさい』という教えです。
私は、『魚をあげないとその人は生きられない。』と勝手に決めてかかっていたのだと、その指摘を受けて気がついたんです。
そして、それは、(その人にずっとずっと魚をあげ続けられるのか?)、(あげ続けたいのか???)という自分への問いにも繋がりました。
「知識や情報を与えることが、今のその人にとっての最善策か?」「それとも、知識や情報は十分。それをどう活用したらいいかを教える必要がある段階か?」など、相手の状況との照らし合わせをすっ飛ばしていたんです。
また、相手の『今』しか見ずに、相手の可能性を信じることもできていませんでした。
そして何よりも、自分の現在の状況(それにかけられる時間だったり、労力だったり)や、自分のありたい姿(何を大切に生きていきたいのか)を考えずに、『与えることこそ正義』と思い込んだまま、突っ走っていたわけなんです。
そりゃあ、苦しいわけですよ。
頑張りが報われない場合もあるわけです。
実は、薄々、人の成長を信じていないのは自分なのでは??と気がついていた(何度か自前のノートに書いていた)私ですが、ずっとその問いに真剣に向き合ってこなかったんです。
でも、自分が守りたいものを守る覚悟が固まりつつあった時にやっと、『相手の成長の機会を奪いかねない』、そして『自分のエネルギーの枯渇に繋がる』ような自分の行いを認められたんです。
『与えること=正義』という考え方は、場合によっては、耕してもいない土に種を蒔く行為だし、十分な水分を保っている草木にドバドバと水を与える行為になりかねません。
会社としての目的だったり、そこから見たチームの役割だったり、自分がこの場にいる目的を『俯瞰してみる』こともせず、ただ単に自分の正義をかざしまくっていたんです。
そしてなんとそれが自分を苦しめていたんです!
実はこれって、家庭においても同じことはありそうですよね。
『自分が全部やろう』とすることや、『自分が与える』ばかりしていては、誰かの成長機会や、やってあげたい!という気持ちを挫くことにも繋がるし、自滅してしまう可能性を高めてしまうんです。
もちろん、状況によっては、代わりにやってあげたり、自分の持っているものを差し出すことは、相手にとっての助けとなることも多いにある。
けれど、物事は見る角度(その時の目的)によって、『良い』にも『悪い』にもなり得るんですよね。
頑張っているのに苦しい、には理由がある。
自分の脳内のロジックエラー(上記で紹介した私の長年のロジックエラーは、いかなる場合も【助ける=相手のためになる】というもの)は、なかなか自分では気がつけないんです。
それは、多くの場合、18歳ごろまでに身につけた生存戦略を軸にして現実を見てしまうことが原因です。
子ども時代の私は、苦労しているように見えた母をきっと助けたかったんですね
助けたくてやったことが、母の笑顔に繋がった。
そんな時は役に立てている自分が誇らしく、自分の存在意義を感じられたのかもしれません
私は、大人の言葉が子どもに与える影響を、体感として“とても大きいもの”だと感じていたから、子供を育てる中で、心と脳、そして言葉についての興味を深めていきました。
ある意味、そのことを解き明かさないことに恐怖感を抱くほどに『知りたい!!!』と思っていたんです。
だからこそ、言葉がどのように心と脳に影響するのかを知ることに、ものすごく時間を使ってきました。
そして、そこでたどり着いた学びの中に重要なものがありました。
心(価値観や信念)の発達において、18歳ごろまでの環境(主に親との関わり)からの影響は計り知れない。
けれど、それが永久に変えられないわけではない(=変えられる)。
偉そうに聞こえてしまうかもしれませんが、私自身が上記の証明の一つではあります。
私は、数年前までは、おそらく18歳ごろまでに身につけた価値観や信念、思い込みにより、自分を苦しめていた部分があります。(上記の通り「助けたい症候群」であった過去の私のエピソードが一例。背景となる私の自己紹介はこちら→PROFILE)
けれど、叶えたい自分の未来が見えた時に、自分が実現したい未来をすでに現実に迎え入れている人から視点をもらうことで、その理想の未来の実現に引っかかる価値観や信念、思い込みを見つめ直し、それにより自分の意識が整い、思考が、感情が、行動が変わり、結果、現実も変えることができたんです。
実は、私が尊敬しているシンガーソングライターのGACKTさんも、このようなことをおっしゃっています。
『19まで、ボクは自分のことが嫌いで仕方なかった。けれど、「この肉体で、この自分で生きていかなければならないんだ」と気づいた時に、「1つ1つ【嫌い】な要素を見直して、クリアし、自分を褒めてやれるようになっていこう」と決めた。』(サンクチュアリ出版 『GACKT超思考術』より引用)
これは、18歳ごろまでに身につけた価値観や信念や思い込みを、見つめ直し、手放したり、新たなものを迎え入れたりした、ということだと思います。
19歳で気がつけたGACKTさん。うらやましい。
でも、うらやんでも、自分の人生を歩めるのは自分だけです。
むしろ生きている間に気づけてラッキー
気がつけずに人生を終える方も多くいらっしゃるからです。(こういう時には、『比較』を用いて自分の気持ちを上げたっていい)
GACKTさんの言葉に重みがあるのは、机上の空論ではなく、実体験からくるものだから。
私はそう感じています。
苦しい!は、心の調整機会に直面しているサイン
もし今あなたが『頑張っている』!!!
けれど、そんな中でもなんとなく、『今の状況が一生続くのは考えられない』し、『自分の理想の人生に向かいたいな』とどこかで感じていながらも、なんだか苦しくてグルグルぐるぐるそこから抜け出せない感覚があるなら、向き合う必要のある課題(心の調整機会)に直面しているのかもしれません。
その機会は人生に何度とあるかわかりませんが(人生をどんどん変えている人には訪れるものですが)、私からメッセージを送ることができるならば、その機会を大切にして欲しいなと感じます。
きっときっと、この機会に向き合うことは、あなたの人生を大きく変えてくれるから
読んでいただきありがとうございました
▶︎別途アメブロでオンライン秘書についての情報発信中➡︎ 【アメブロを覗いてみる】 ポチッ

この記事が気になったら
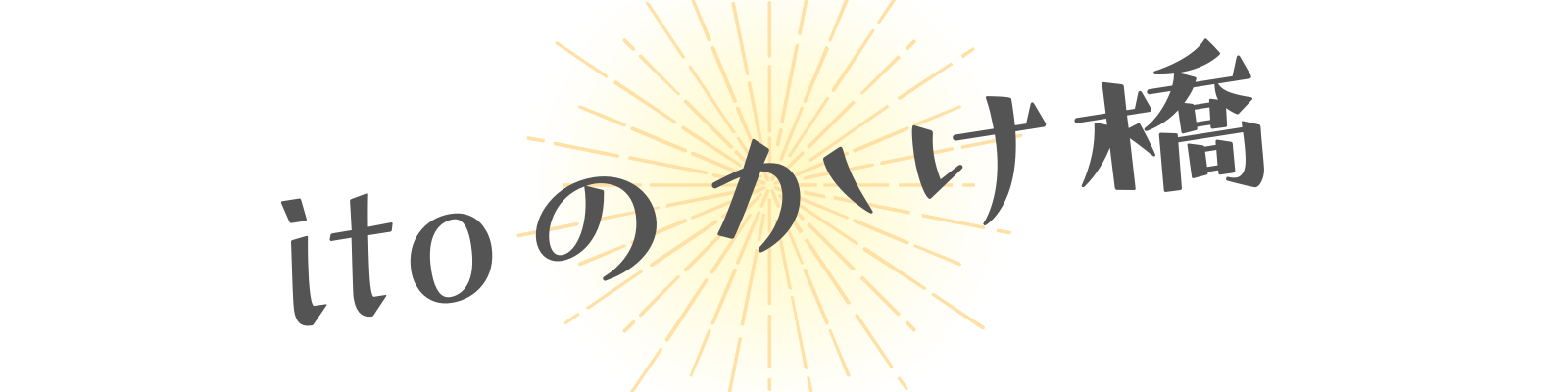

.png)
